�������O�E��l�����n
SuperKEKB�����O
�������O�E��l�����n
SuperKEKB�����O

�����劲���A

�������O�����n�劲/�ēc ��(Kyo SHIBATA)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n�劲 ����
�������l�����n�劲/��R �^��(Makoto TOBIYAMA)
��E�F�����팤���{�� �������l�����n�劲 ����
SuperKEKB�v���W�F�N�g�́A�z�d�q�Ɠd�q���Փ˂����Đ��������B���Ԏq�����܂ޔ����������ڍׂɌ������邱�Ƃɂ��A���܂Ŋϑ�����Ă��Ȃ������������ۂ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B���̖ړI�ŗp�����郊���O�^�Փˉ����킪SuperKEKB������ł��BSuperKEKB�́A�ɂ߂đ�����B���Ԏq�E��B���Ԏq������B�t�@�N�g���[�iB�H��)�ŁA����������܂ł̐���������傫�����킷��̂ŁA�X�[�p�[B�t�@�N�g���[�ƌĂ�ł��܂��B
SuperKEKB�́A������3km�̓d�q�p�Ɨz�d�q�p�̓�̃����O�^������ƁA���̃����O�ɓd�q�E�z�d�q������������ˊ킩�琬�藧���Ă��܂��B�n��12m�Ɍ@��ꂽ1����3km�̃g���l���̒��ɂ́A��̉~�`�����킪����Őݒu����A���ꂼ��̉�����̒���d�q�r�[��(�G�l���M�[��7GeV)�Ɨz�d�q�r�[��(4GeV)���قڌ����ŋt�����Ɏ��܂��B��̃r�[���̓����O�̈�_�݂̂ŏՓ˂���l�ɐv����Ă���A�Փ˓_�ɂ���Belle II���o�킪�Փ˂ɂ���ċN����f���q�����𑨂��܂��B
SuperKEKB�ł́A���������r�[���T�C�Y���قڃE�C���X�T�C�Y�܂ōi�鎖�A�܂��r�[���d����啝�ɏグ�鎖�ɂ��AKEKB������̐��\�{�܂ŏՓ˕p�x(���~�m�V�e�B�j���グ�鎖��ڎw���A����𑱂��Ă��܂�

�����O���[�v

�O���[�v���[�_�[/�n� ��(Ken WATANABE)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n �y����
SuperKEKB������i�����PF-AR������j�ɂ�������ː��h���ړI�Ƃ������S�V�X�e�����\�z����Ƌ��ɁA������̉^�]�ɏd�v�ȋA��p���A�d�͎�d�ݔ��Ȃǎ{�݁E�C���t���X�g���N�`���[�̈ێ����{�ݕ��Ƌ��͂��Ȃ���S�����Ă��܂��B��X���S�����������͏�ɍō����\���X�V�������邽�߂̉������s������ɂ���A���ː��V�[���h�̌��݂��܂߂����S�V�X�e���̍\�����������_��Ȕ��z�ł�茘�S�ƂȂ�悤�œK�����Ă����K�v������܂��B
�܂��A���L�����p�X�ő�̉�����̎{�݁E���S��S���Ƃ��āA�@�\�ɂ�����e����S�Ɩ��Ɋւ���d�ӂ��S���Ă���A�����E�v���W�F�N�g�̊_���������������Ă���܂��B

�O���[�v���[�_�[/�ēc ��(Kyo SHIBATA)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n ���� �����劲(��) �Z�p���劲(��)
SuperKEKB�̂悤�ȃ����O�^������ł́A�d�q��z�d�q�̃r�[���͋������r�[���p�C�v�̒�������Ă��܂��B�r�[���p�C�v���ɋC�̕��q����ʂɑ��݂��Ă���ƁA�d�q��z�d�q�͋C�̂̕��q�Ƃ̏Փ˂ɂ��i�s�������傫���Ȃ����Ă��܂��A�����ԃp�C�v���ɂƂǂ܂邱�Ƃ��ł��܂���B�����ŁA�r�[���p�C�v���̋C�̕��q�����炵�A�^���Ԃɂ��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B�Ⴆ�Έ��͂�1������1�C���ɂ���ƃr�[����10���Ԉȏ��������ɗ��߂Ă������Ƃ��ł��܂��B���̂悤�ɁA�r�[���p�C�v��^��ɂ��A����Ɉێ����邱�Ƃ�������^��V�X�e���̑傫�Ȗ����ł��B���͂��Ⴂ�ƁA�r�[��������ɕۂ��ʂ�����܂��B�^��V�X�e���́A������̊�{�ƂȂ�V�X�e���̈�ł��B
�O���[�v���[�_�[/���� �S��(Tetsuya KOBAYASHI)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n ����
���ˌ����o�����ƂŃG�l���M�[�������r�[���ɁA�����g������ʂ��ăG�l���M�[����������V�X�e���S�̂ɂ��āA����n�ł���LLRF(��x��RF����n)�̌����E�J���E�ێ��A�܂��V�X�e�������o���r�[���s���茻�ۂɂ��Ă̌�����i�߂Ă��܂��B
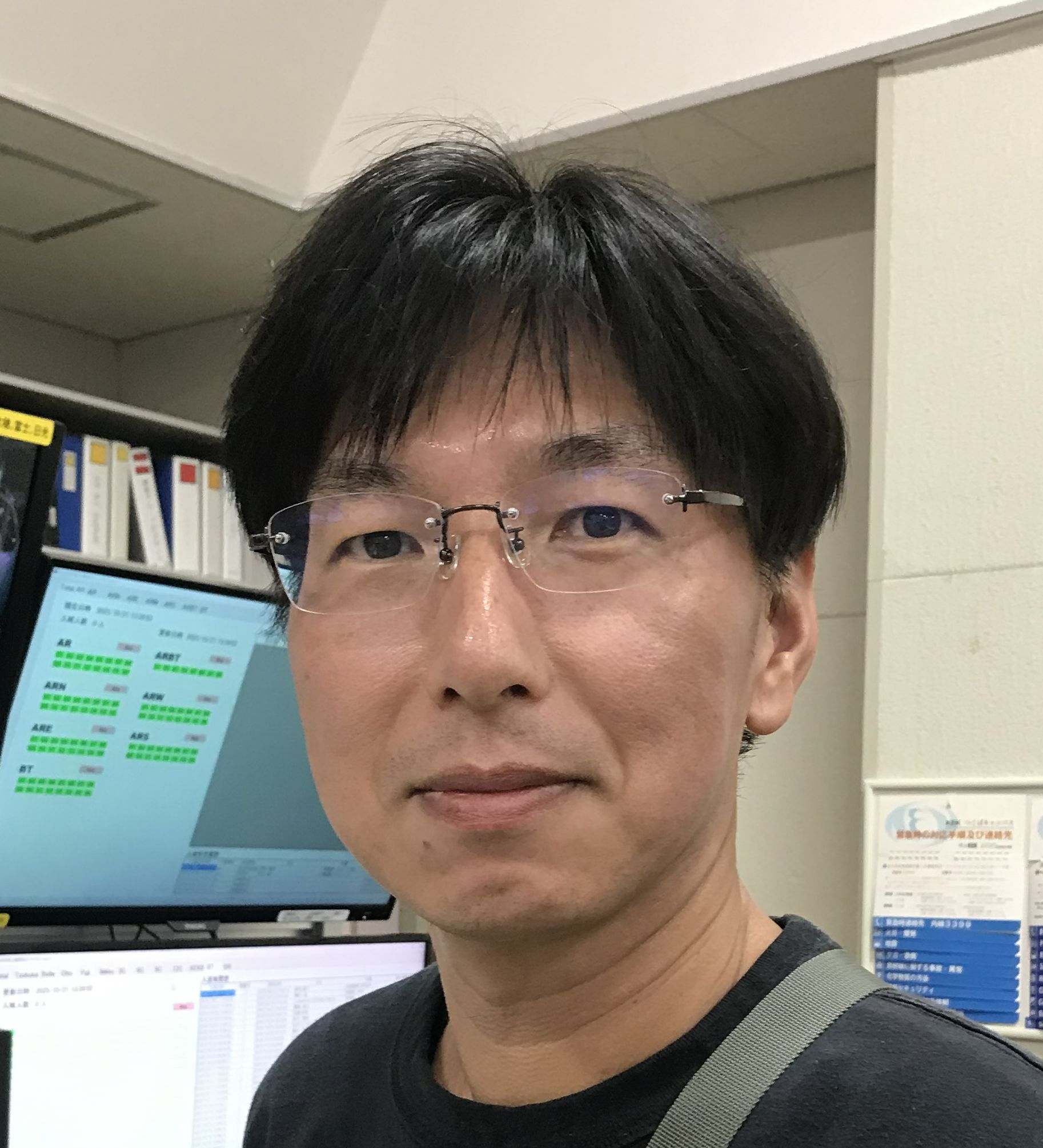
�O���[�v���[�_�[/�n� ��(Ken WATANABE)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n �y����
SuperKEKB������̃����O���ɂ���30��̏�`���iARES�j�A8��̒��`�����������DR�ɂ���2�̉�����UHF�т̑�d�͍����g�d�́i�A���g�j���������Ă��܂��B���̑�d�͍����g���ɂ́A�A���g�ł͐��E�ő勉��1.2MW�N���C�X�g�������v31�{�g�p���Ă���A���Y�N���C�X�g�����̊J���A���̕ی��H�����˂闧�̉�H�ƌĂԓ`���n����є��������������g�d�͂����S�ɋz�����邽�߂̃_�~�[���[�h�Ȃǂ̌����A�J���A�ێ����s���Ă��܂��B�{�V�X�e���͎{�@�B�ݔ��Ɠ��l�ɃC���t���X�g���N�`���[�Ƃ��Ď�舵���A�Q�������S����L���邱�Ƃ����߂��܂��B�����ōł��d�v�Ȍ������ڂ̈�Ƃ��āA���\�N�ɓn��^�]���Ԃ��l�������e�@��̒�������������܂��B���ɐ��₷��n���ɂ����ēd�C�I�E���w�I�������l�����������Ǘ��A���̌n���Ŏg�p����@��̍ޗ��E�\�ʏ������@�̊J�������̃J�M������A���̗ǂ������f���邽�ߒ����ɂ킽�郂�j�^�����O���s���Ă���܂��B
�܂��A���V�X�e���͗��j�I�Ȍo�܂���PF-AR������ɂ��g�p����Ă���A��X�̃O���[�v�͂�����̃V�X�e���̉^�]�E�ێ��Ǘ��ɑ傫���v�����Ă��܂��B
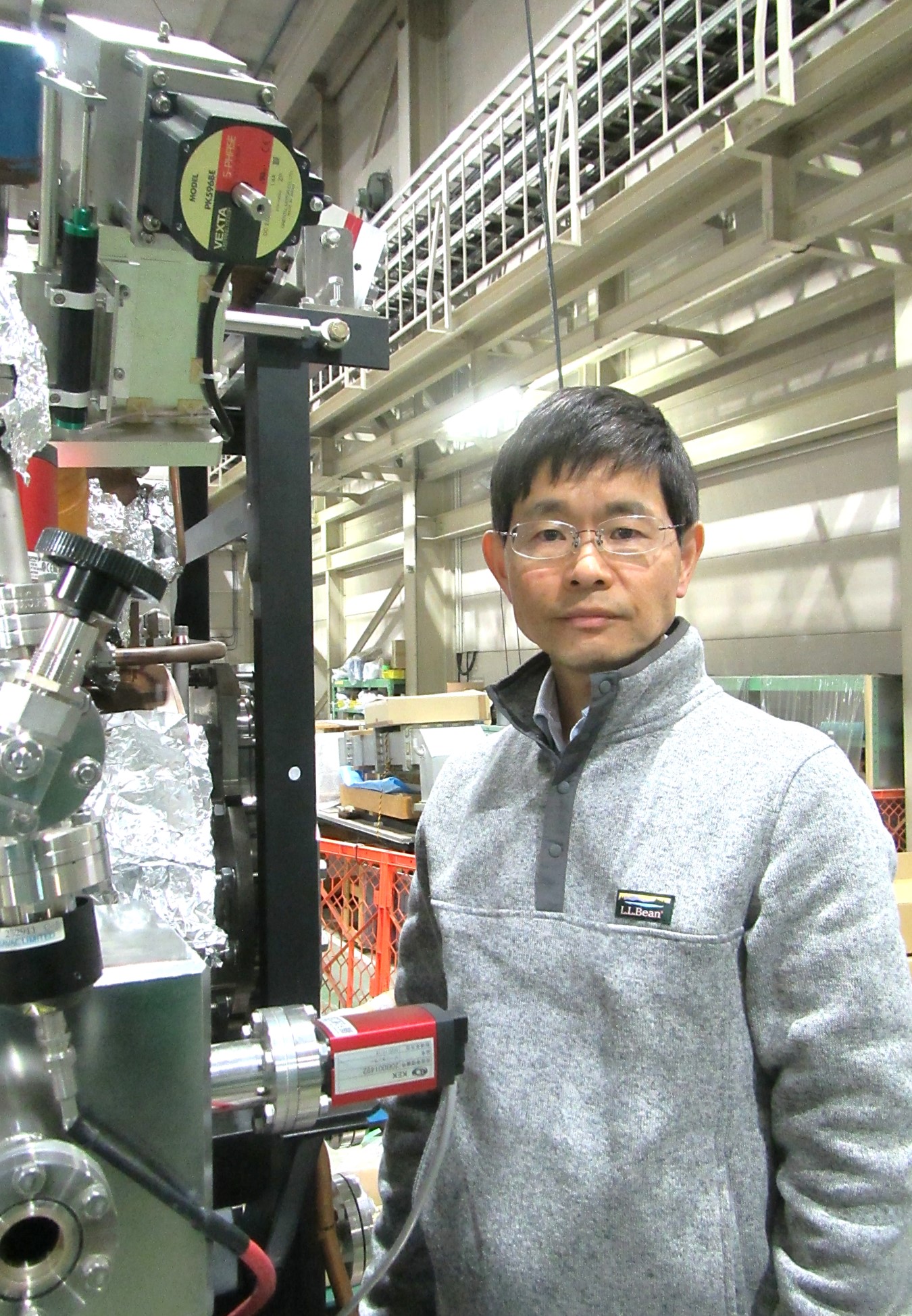
�O���[�v���[�_�[/���� �N��(Tetsuo ABE)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n ����
SuperKEKB������œd�q�����O�E�z�d�q�����O�����Ɏg���Ă����`���̉����́A��d�̓}�C�N���g�𗭂ߍ��ށu�����v�A���ۂɃr�[������������u�����v�A�����Ă��̗��҂��q���ŗL�Q�ȃr�[���s�����}������u�����v���琬��O�A�V�X�e���ł��B����́A���E�I�ɂ��B�ꖳ��ŋ��͂ȍ����g�����ł��B�p��ŁuAccelerator REsonantly coupled with energy Storage�v�ƌ������߁A�u�A���X�iARES�j�v�ƌĂ�ł��܂��B
�A���X�͑O�l�����̑�d���r�[��������I�ɉ������邽�߁A�������\�𐧌������鍂���g���̐^��≏�j��ɂ��āA���̔������J�j�Y���̉𖾂�A�V�����Ď��E�f�f�V�X�e���̊J�����s���Ă��܂��B
�O���[�v���[�_�[/���e �݂���(Michiru NISHIWAKI)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n �y����
�����͋��ɓd���������ēd�C�����������q�i�d�q�A�z�d�q�Ȃǁj��d���͂ʼn������鑕�u�ł��B���`���́i�j�I�u�j�͓��Ȃǂ̋����ɔ�ׂĂ͂邩�Ɍ����悭�����d�������邱�Ƃ��ł��܂��B���̐����𗘗p���Ē��`������������܂����B
KEKB������ł�8��̒��`��������1.4�A���y�A�̓d�q�r�[�����������邱�Ƃɐ������܂����BSuperKEKB������ł�2�{��2.6�A���y�A�̓d�����������܂��B��d���r�[��������ɉ�������Z�p�����߂��Ă��܂��B

�O���[�v���[�_�[/���� ����(Kota NAKANISHI)
��E�F�����팤���{�� �������O�����n ����
��^�w���E���Ⓚ�V�X�e���́A1988�N�i���a63�N�j�Ƀg���X�^��������v��̒��`�������̗�p�V�X�e���Ƃ��ē����������ɐݒu����܂����B�����́A�Ⓚ�\�� �y4 kW at 4.4 K�z �̐ݔ��Ƃ��ăX�^�[�g���܂������A1989�N�i�������N�j�ɒ��`�����������݂��ꂽ���Ƃɔ����A�������̒��ՊE�^�[�r���������Ⓚ�\�� �y8 kW at4.4 K�z �̗Ⓚ�V�X�e���ɑ�������A7�N�Ԉ���ɉ^�]����܂����B���̌�A1998�N�i����10�N�j����́AB�t�@�N�g���[(KEKB�j�̒��`�������̗�p�p�ɍė��p�E�^�]����A2007�N�ɂ͐��E�ŏ��߂�KEKB�Ŏ��p�����ꂽ���`���N���u�̗�p�ɂ��g�p����܂����B2010�N�i����22�N�j��KEKB�^�]��~�܂łɁA�{�w���E���Ⓚ�V�X�e���̑��^�]���Ԃ�22�N�Ԃ�110,000���Ԃ��܂����B�������ASuperKEKB�ł����`�������̗�p�Ɏg�p���邽�߁A�����Ԃ̈��肵���^�]��ڎw���ėⓀ�V�X�e���̊J���E�ێ�E�_�����s���Ă��܂��B
�O���[�v���[�_�[/�X�c ���v(Akio MORITA)
��E�F�����팤���{�� �������l�����n ����
�d�q�Ɨz�d�q���Փ˂��Ă�������B���Ԏq�������悤�ɁA�����̑��u���u���ɒ������Ă��܂��B������̊e���u�ƒ������䎺�̊Ԃ̋��n�������Ă���Ƃ������܂��B���u�̐�����1���A������̐���20���ɂ��Ȃ�̂ŁA�w�߂��m���ɓ`���A����L���ɗ��p���邽�߂ɕ��G�Ȑ���V�X�e�����K�v�ƂȂ�܂��B
����͌v�Z�@�����ӂƂ��镪��Ȃ̂ŁA�������̌v�Z�@���g���Ă��܂��B�T�[�o�v�Z�@10��A�S�̑���p�v�Z�@20��A�����Ԏ��������p�v�Z�@100��A�������Ȃ���e�ʍ����l�b�g���[�N���u�A����ɐ����̃}�C�N���R���s���[�^���g���Ă��܂��B���ۓI�ɋ����J������Ă���EPICS�Ƃ����\�t�g�E�F�A���g���Ă��܂��B
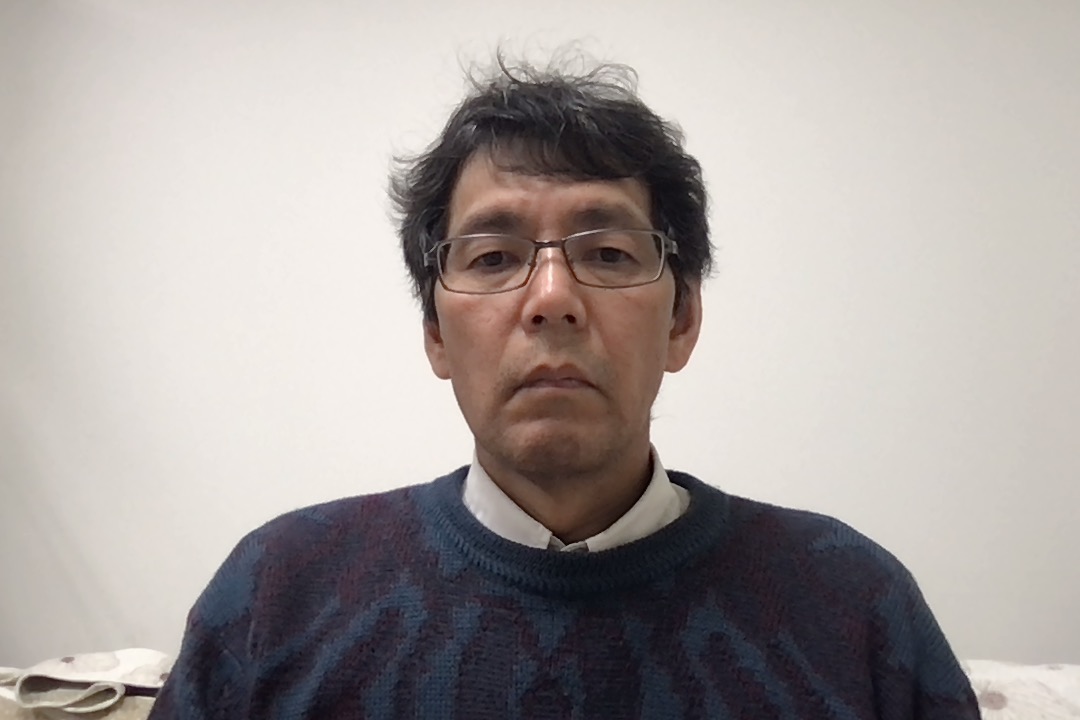
�O���[�v���[�_�[/���a�c ����(Masafumi TAWADA)
��E�F�����팤���{�� �������l�����n �y����
�Փ˃����O�iHER�ALER��2�̉~�`������j�ɂ͓d�q����їz�d�q��~�ς��܂��B ���^������ʼn������ꂽ�d�q����їz�d�q�� �Փ˃����O�܂ʼn^�сA���˂��邱�Ƃ��r�[���A���V�X�e���̖����ł��B�����O���ł́A���˂ɕK�v�ȃp���X�d���V�X�e���A�܂��r�[����1���ň��S�Ɏ̂Ă邽�߂̃r�[���A�{�[�g�V�X�e�����S�����Ă��܂��B
�O���[�v���[�_�[/��R �^��(Makoto TOBIYAMA)
��E�F�����팤���{�� �������l�����n ���� �����劲(��)
SuperKEKB�̂悤�Ȑ����ȉ�����ł́A�������\���������邽�߂ɁA�r�[���ʒu�𐳊m�ɂ������ɑ��肵�A�r�[�����w�O���[�v�ɒ��邱�Ƃ����ɑ厖�ł��B�d�q�����O�A�z�d�q�����O���ꂼ��450�ӏ����x�ɂ���ʒu���j�^�[�ł̑��葕�u�̊J���A�ێ��A�������s���Ă��܂��B
�܂��A�d�q��z�d�q�́A�o���`�ƌĂ��d�q��z�d�q�̉�ƂȂ��Ď��Ă��܂����A���̃T�C�Y(�K�E�X���z�Ƃ����Ƃ��̕W�����ŁA����������6mm���x�A��������0.3mm�A��������0.01mm���x)�𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃ���A�r�[���������Ă���d����̏��邱�Ƃ��o���܂��B���̂��߂ɏd�v�Ȏ�ɃV���N���g�������˂��ϑ�����A�����y��X���̃��j�^�[�̊J���A�����A�ێ������Ă��܂��B
�o���`���m�̊Ԋu�͒ʏ�^�]���ł�1.2m���x(4ns)�ŁA��s����o���`���c�����d���g�ɂ���Č㑱�̃o���`���h�����錻��(�o���`�����s����)��}������o���`�t�B�[�h�o�b�N�V�X�e���̊J���E�����E�ێ����A�r�[�����j�^�[�O���[�v���S�����Ă��܂��B
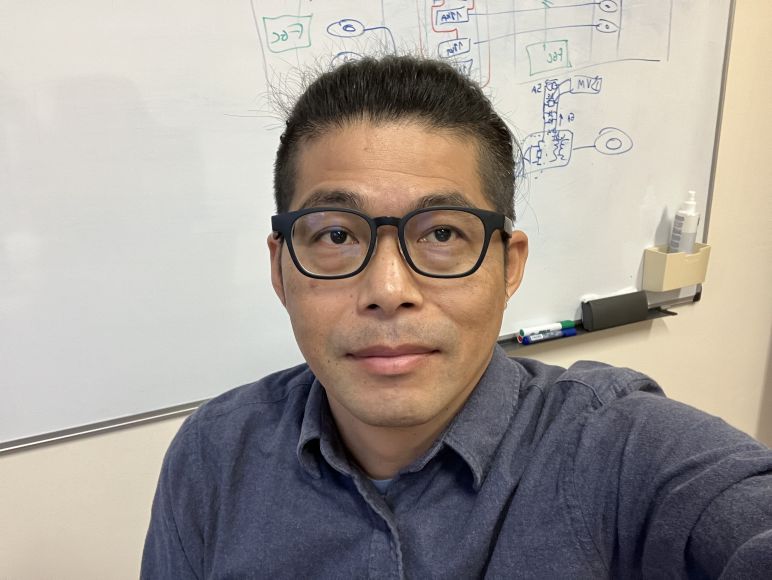
�O���[�v���[�_�[/���� �O(Shu NAKAMURA)
��E�F�����팤���{�� �������l�����n ����
SupeKEKB�ł̓g���l�����ɓd�q�^�z�d�q�����O���킹�Ė�300��̕Ό��d���A��900��̎l�ɓd���A200��ȏ�̘Z�ɓd����ݒu���A���ꂼ��̃����O�̃r�[���𑀍삵�Ă��܂��B���̑��Ɏl�ɓd���̂ƂȂ�ɂ͏��^�̕Ό��d���i��d���j�𑽐��ݒu���A�e�r�[���O���̔��������s���Ă���ق��A�l�ɓd���^�Z�ɓd���ɂ͌��w����s�����߂̕⏕�R�C����������Ă��܂��B�����̓d���͂��ׂĐ��x�悭���H���ꂽ���̂ŁA�̍����ł��邾�����������Ă��܂��B�܂��A�ݒu�O�ɂ͎��ꑪ����s���Ă��ׂĂ̓d���̓����]�����s�����̂��A�g���l������0.1mm�ȉ��̐��x�Ő����t���Ă��܂��B
�����̓d����⏕�R�C���ɓd���𗬂��d���͑召���킹��3000��߂�����A���ꂼ��^�]�ɕK�v�Ƃ���鎥�ꐸ�x�������߂ɗv���ɉ�����1~100ppm�̐��x�œd����ݒ�A�ʓd���s���Ă��܂��B�ʓd���Ă���d���l�������x�̐��x�Ōv������K�v�����邽�߁A�����x�̓d�����j�^�V�X�e����p�ӂ��A�펞���j�^�����O���s���Ă��܂��B
�����d���E�d���̈ێ��Ǘ���V�K�J���̑��A�g���l���̔N��������U���̑���ȂǓd���̃A���C�������g�⎥��̕ϓ��Ɋւ��鑪����s���Ă��܂��B
�O���[�v���[�_�[/��� �r��(Toshiyuki OKI)
��E�F�����팤���{�� �������l�����n �y����
SuperKEKB�ł́A�d�q�Ɨz�d�q�r�[���̏Փː��\�i���~�m�V�e�C�j��KEKB�̐��\�{�܂Ō��コ���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��܂��B���ׂ̈�2�̃r�[���͏c�����ɗz�d�q/ �d�q��48/62�i�m���[�g���܂ōi���܂��B�������������ׂɁA�Փ˓_�̈�ԋ߂��ʒu�ɑ�R�i�F�X�Ȏ�ށj�̒��`���d�����ݒu����Ă��܂��BSuperKEKB�ł́A�r�[���Փ˓_�̍��E�ɃN���C�I�X�^�b�g��KEKB�Ɠ�����1��Âz�u����Ă��܂����A�e�N���C�I�X�^�b�g�̒��ɂ͒��`��4�ɓd����4��A���`���\���m�C�h��1��A���`���R�C����20��g���܂�Ă��܂��B
�����v��Ƃ��āA��蒴�`���]�ډ��x�̍���Nb3Sn���ނ��g�������`���ŏI�W�����̊J����KEK���̒ቷ�Z���^�[�A�@�B�H��Z���^�[���͂��߁A�����̑�w�A�܂��A�C�O�̌����@�ւƋ��͂��Ȃ���i�߂Ă��܂��B

�O���[�v���[�_�[/�吼 �K��(Yukiyoshi ONISHI)
��E�F�����팤���{�� �������l�����n ����
SuperKEKB������̖ڕW���\��B�����邽�߂̃r�[�����w�v�A��������������
�̐��\�B���̍H�v����ђ��������s���܂��B
�݂Ȃ���́A�J�����̃����Y���ǂ̂悤�ɂ��Đv����A�Ȃ������Y���������g
�ݍ��킳��Ă��邩�����m�ł��傤���B����́A���ꂢ�Ȏʐ^���B�邽�߂ɑn��
�H�v����Ă��邩��ł��B��������J�����Ɠ����悤�Ƀ����Y�Q�ɑ�������d��
�ΌQ��g�ݍ��킹�ăr�[�����w�v���s���܂��B�܂��A��������������͐v��
��́A�K���덷������܂��B���̌덷�������\��������w�͂���X�s��
�Ă��܂��B������A�R�~�b�V���j���O�ƌĂт܂��BSuperKEKB������̃R�~�b�V
���j���O�ɂ́A3�n��4�n�̋����A�Z�p�E�����Q�����A24����3���ŎQ�����Ă�
�܂��B�R�~�b�V���j���O�E�O���[�v�͂��̒��j�Ƃ��ăr�[�����w�̌����A�r�[��
����̏����g�����r�[�����w��A�r�[���O����Ȃǂ̃c�[���J���A���~�m
�V�e�B�����ׂ̈̏Փ˒����c�[���̊J�����s���Ă��܂��B