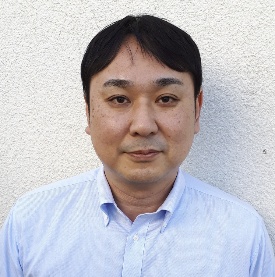
加速器第一研究系主幹

加速器第二研究系主幹
研究グループ
MR電磁石電源グループ

MR RFグループ

MR入射/FXグループ
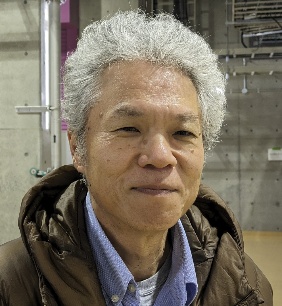
MRモニターグループ
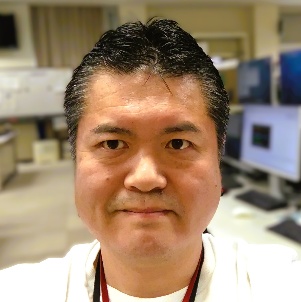
MR真空グループ
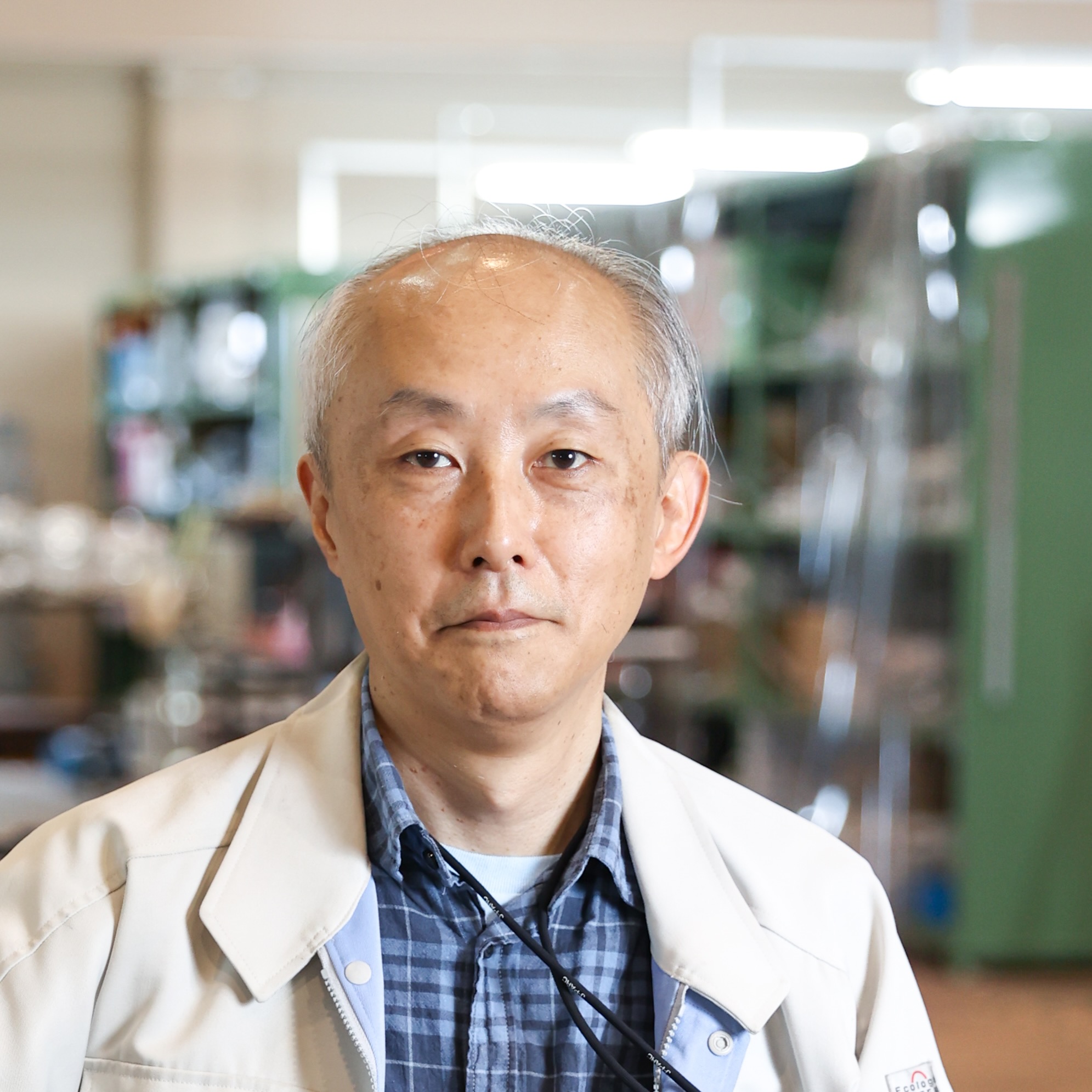
MR制御グループ
MR 3-50BTグループ

システムコミッショニンググループ

MRビームコミッショニンググループ

MR SXグループ

リニアックグループ

ミューオンリニアックグループ

iBNCT加速器グループ
